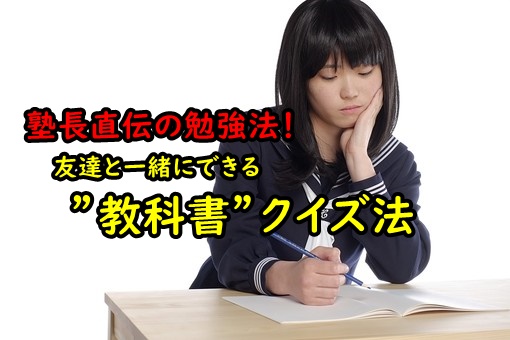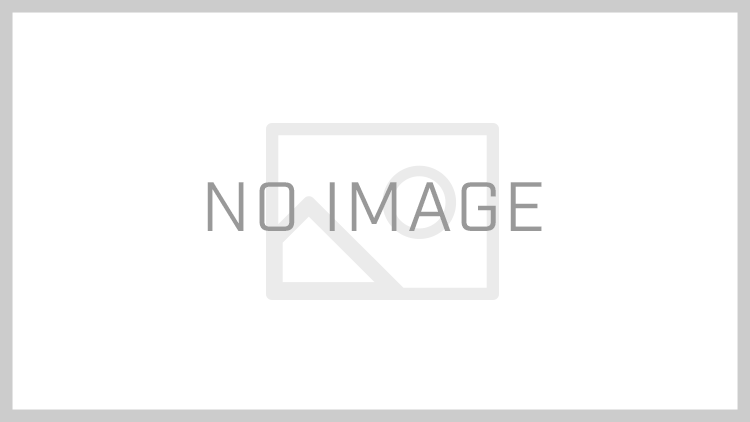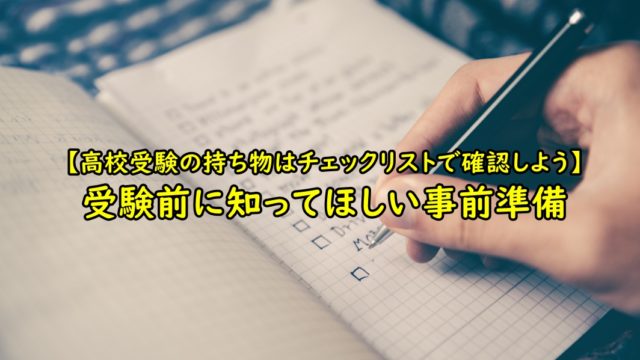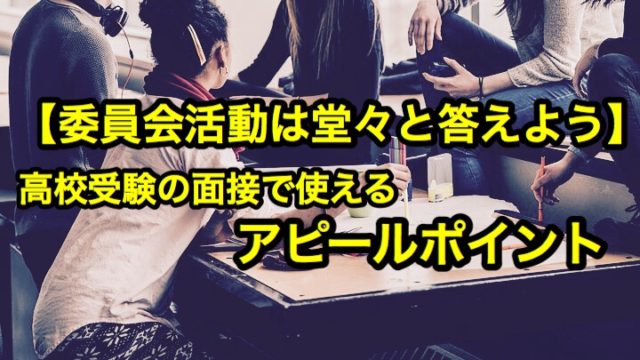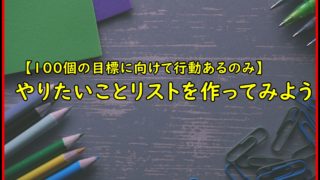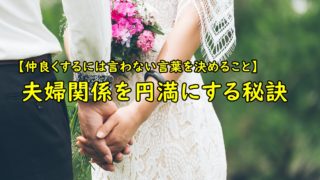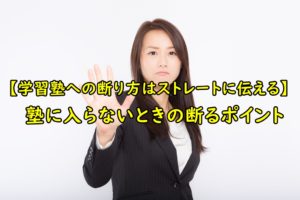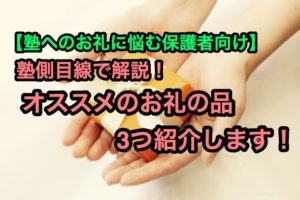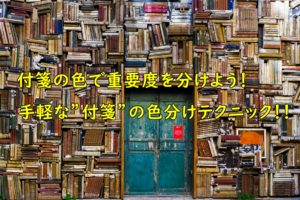勉強が好きな子!!
って手を挙げてもらうとほとんどの人は手を挙げません。
でも、勉強は頑張りたいという、そこのあなた!
あなたの悩みを解決します!
学習塾の塾長を3年近くやり、生徒数が100名近くの大きな塾で日々、指導をしていました。
その時に提案した「クイズ!教科書の太字はなんだろな」を今回は教えていこうと思います。
お友達と気軽にできるクイズで、使うのも手元の教科書だけでOK
自習室ではめちゃくちゃ盛り上がって勝手に成果が上がるおかしな勉強法!
やり方は2つだけなので、ぜひやってみてくださいね。
考案のキッカケは友達を助けたかったから
中学のときの結城には、6人の親友がいました。
6人はそれぞれよ得意な科目が別々のメンバーだったんです。
勉強しようとすると
- 1人は得意
- あとの5人は不得意
という形だったので、1人が指導をする形でサポートしました。
その時に、発案したのがクイズ形式で問題を出すと言うもの
先生のように前に立ち「クイズ」を出しながら理解を深める方法でした。
結果は、それぞれの不得意科目が100点満点中、20点台だった時に比べて、70点まで上がったので効果は期待できます。
教科書の”黒太字”の前後の文章を疑問形で質問する。
例えば、社会なら
「中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を暗殺し、蘇我氏の体制を終わらせました。この内容を大化の改新と言います。」
となっているとする。
クイズでは、黒太字になっている大化の改新の前の「中大兄皇子~終わらせました」までの内容を疑問形で質問します。
「中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を暗殺し、蘇我氏の体制を終わらせた事件を何と言いますか?」
という形です。
この点のメリットは7つ!
- 教科書ベースの問題作成が多いため、黒太字を抑えておくことで点数に繋がる
- テストの問題が質問形式で問い掛けるため、事前に練習が出来る
- ただ教科書を読むよりもいくつかの工程を挟むため、記憶に残りやすい
- 友達同士の問題の出し合いのため、先生の言葉よりも受け取りやすい
- 問題を出す側が1番理解出来る勉強法
- アレンジを効かせる問題も作れる
- 問題を作ることで、作る側が気づいてほしいポイントを把握出来る
やり方のテンプレート
塾生には最初に10個のルールだけ伝えて、後は自由にやらせてました。
- 問題にする箇所を決める
- 言葉を考えて発表する
- 出題者は発表後に問題の出し方を見直す
- 解答者は発表後に答えを考える
- 解答者を1人決めて発表
- 解答発表後に正解を伝える
- 出題者が解答内容の説明をする
- 間違えても笑わない!
- 間違えていたら手を挙げて、理由を伝えてあげよう
- 問題や答えが出ない友達には周りがフォローしてあげよう
これをルールとしてやってました。
意外な効果は「生徒が勝手に先生をしてくれる」
塾の生徒が複数人で集まるときは、みんなでワイワイ言いながらやってました。
自習室で盛り上がっていたので、テスト直前の勉強会では、
“生徒が得意科目の先生になれる日“と題して、総勢150名の生徒が6つのグループに分かれて問題を出し合ったりしました。
他の学校の生徒との交流のキッカケに
塾の立地が4つの中学の真ん中だったので、全然知らない学校の生徒たちも混ざってました。
- 学習範囲が違う
- 後に勉強する箇所
- 復習のために参加
などの理由が大きかったです。
それぞれの生徒たちが協力して勉強し、仲良くなる姿を多く見るようにもなりました。
得意な教科の質問を、別の学校の友達に聞く光景なども何度か見るようになりました。
生徒達自身の勉強意識が勝手に高くなるので効果的でした。
勉強は「自分から動く」ことで成果に繋がる
学習環境は、自分でコントロール出来ないと思っている人が多かったりします。
結城も。その1人でした。
でも、仕組みを作ってキッカケを与えるだけで大きなパワーで動きます。
実施したときのメンバーは2人
塾で実施したときのメンバーは最初、2人でした。
仲良しの女の子同士が2人で勉強していました。
- 一緒に勉強する思い出作り
- 協力して点数を上げる仲間
- 楽しい時間を過ごせる
以上の勉強方法を伝えました。
効果が出ることは結城自身が学生時代に体験済み。
だからこそ、かなり自信はありました。
そして、1年後にはテスト前の勉強会で150名の生徒が参加してくれるようになりました。
大きい規模になっても、ルールはみんな守ってくれている。
その事実だけでも嬉しいものです。
勉強の形っていくつもある
今回の教科書を使った勉強法は以下の通りです。
- 問題にする箇所を決める
- 言葉を考えて発表する
- 出題者は発表後に問題の出し方を見直す
- 解答者は発表後に答えを考える
- 解答者を1人決めて発表
- 解答発表後に正解を伝える
- 出題者が解答内容の説明をする
- 間違えても笑わない!
- 間違えていたら手を挙げて、理由を伝えてあげよう
- 問題や答えが出ない友達には周りがフォローしてあげよう
勉強には次の4つの要素を含んだ方法が一番勉強効果があります。
- 書く
- 読む
- 見る
- 聞く
のイメージが強く見られます。
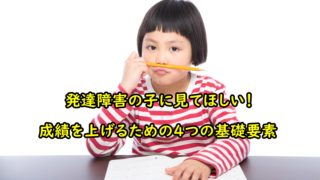
複数の作業を同時に満遍なくクリアしていると成果に繋がりやすいです。
勉強を楽しく進めるために、アレンジを加えてみた勉強法をぜひ試してみてくださいね
あなたの人生を「楽」に「素直」に生活できるように、ちょこっとのエッセンスを届けるサイトです。
生活、暮らし、お金などの情報を盛大に盛り込んだものをお届けします。